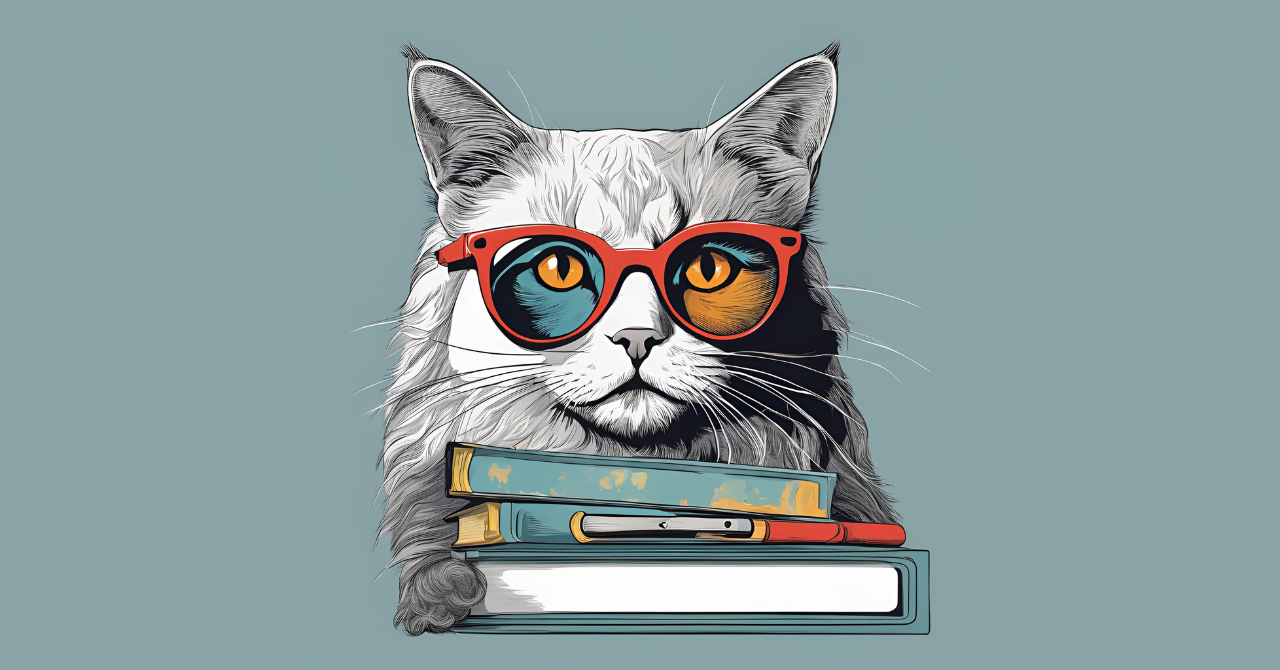最近時間があるので、もともと興味があった曲作りをしてみたり、いろんな本を読んだり、特定のテーマについて考えたりすることが増えました。 そのなかで、時間の流れ方について僕の中で、いったん現時点での答えとなる価値観が見いだせたので、それを紹介します。 時間をどう捉えるか。過去が今を押しているか。未来が今を引っ張っているか 時間の流れ方は2種類。 過去から押されるか、未来に引っ張られるか この2つです。 時間は過去から未来に向けて流れていくことは絶対変わらない原理ですが、その時間の流れるパワーがどこを起点にしているか、は2種類あるということです。 正直これは、物理的にそうだというよりは、時間をどのように捉えているかということになると思います。 めっちゃわかりにくいと思うんで、図にしてみました! 過去起点の時間の流れ方はこんな感じで、 未来起点の時間の流れ方はこんな感じです。 過去は押している、未来は引っ張っているというこの状態をそれぞれ、過去推進・未来牽引と名付けました。 過去推進にとって、未来は過去の延長線上にあり、今自分にできることをやるという、少し受け身な姿勢になりがちです。 対して、未来志向は、未来像を設定したうえで、その未来像と今の自分の差分を埋めるための行動をしていくという比較的アクティブな姿勢であると考えてます。 過去推進・未来牽引の考え方はどちらも重要 恐らく、ビジネス書をよく読む人とかは特に、今の説明を聞いて「よし、未来牽引型の時間の流れを意識するぞ!」と、考える人は多いんじゃないかなと思います。 みんなビジョンを作れ!とか言いますもんね(笑) 理想の将来像を定めること、これは僕もよりよい人生を歩みたいのなら必須だと考えてます。 でも、未来牽引の考え方のみでもちょっと微妙だと僕は考えてます。 あくまでも過去推進と未来牽引、どちらの考え方もいい感じのバランスで取り入れる必要があります。 どちらも得意な領域が違うからですね。 例えば過去推進は、過去の積み重ねが前に進めるパワーになります。なので、過去推進の考え方が強いと継続力がある人間になりやすいです。 反対に未来牽引は叶えたい未来像との差分を埋める力が働くので、行動力がある人間になりやすいです。 この2つの力はより良い人生にするためにはどちらもバランスよく身に着ける必要があります。 仮に未来牽引だけで過去
忙しいことに満足している人に言いたい。立ち止まる時間も人生において必要なんじゃないだろうか?
どうも、ばんぶうです。 実は私、昨年末に退職をいたしました。来月から新しい職場となります。 いわゆる転職をいたしました。 それによって、直近1カ月くらい仕事をしていない期間があったのですが、そこで感じたことをこちらの記事に書き綴ろうかと思います。 簡潔に伝えたいことをまとめると、可能であれば、積極的に「何もすることが無い時間」を作ることは人生にとって確実にプラスになるということです。 前職ではITベンチャー企業に勤めていたのですが、仕事量はかなり多く、平日は職場と家の行き来となり、休日もほとんど仕事のことばかり考えているような生活でした。 今思い返すと、かなり切羽詰まった生活をしていたような気がしています。 もちろんその生活によって、ビジネスの造詣は深くなりましたし、思考スピードも著しく早くなったため、得られるものは大きかったです。 ただ、どうしても思考の深度は浅くなりがちで、自分が進んでいる先が本当にたどり着きたい場所なのかどうかを考える余裕もなかったような気がしています。 Microsoftを立ち上げた、かの有名なビルゲイツは「Think Weeks(考える週)」という時間を積極的にとっているそうです。 1週間ほど山に籠って外界からの情報をシャットアウトし、アイデアの整理や新しい技術、ビジネス戦略について深く考える時間として確保しています。 ビルゲイツのような、日々の仕事の忙しさから解放される、まとまった時間をとること。 それは私自身、転職というきっかけから生じた「空白の期間」を得たことで、かなり有意義なものであると体感できました。 空白の期間でやった方がいいこと 人生の羅針盤を作る 空白の期間でやった方がいいこと1位は人生の羅針盤を作ることです。 少し大げさに書きましたが、今後手に入れたいこと、やってみたいことなどを考えてまとめることです。 また、どんな人間になりたいかという「人としての在り方」を深く考えることもすごく重要になります。 人生の羅針盤と書いてはいますが、1年後の自分をイメージするとかでも大丈夫です。 「未来の自分はどんな場所で、どんな考え方をして。どんなことをしていて、、、」という未来を描きましょう。 できればイメージしたことはノートにペンで書きなぐってみてください。 綺麗さとかそんなのは考えずに、とりあえず頭の中を吐き出すみたいな感じで。 自
「共感力」というものを99%の人間は理解できてないという事実
”共感”できてますか? と、いきなり言われてびっくりしますよね(笑)今回は共感について話していきたいと思います。 ビジネスでも恋愛でも、人とコミュニケーションをする上で共感することが重要ということは、どこかしらのタイミングで目にしたことはあるかと思います。 ただ、共感とひとくくりにするのはいいものの、実際どのような状態が共感したと言えるか、を深堀している人は僕の周りの人を見渡しても体感ほとんど0に近いです。 実際、本質的に人に共感するといいうことは「マジで、めちゃくちゃ難しい!」んですよね 今回は、僕が個人的に定めている共感のレベルを紹介していきます。 共感力の4つのレベル 目次 レベル①:相手の話をただの音として聞いている状態 ここが、共感力の最初のステージになります。相手の話を、ただの音として認識しており、話の背景や情景・その時生じた感情などを何ひとつ想像せずに聞いている時です。 このような場合はあいづちもテキトーで、言い方やリアクションの大きさも、相手の話している内容とマッチしないです。 レベル②:相手の話している内容に適切に相槌ができる状態 レベル①から成長し、ある程度相手の話を想像してあげられる状態です。適切な言い方やリアクションでしっかりあいづちをしているので、相手にも「わかってくれてるな」と感じてもらえないです。 ただ、相手のトークに対して受け身の状態ではあるので、話に広がりがなくなり、薄いコミュニケーションしか取れない可能性があります。 レベル③:相手の話を引き出すために質問を投げかけれる状態 ここまでくるとかなり共感力は高いと思います。相手の話を聞いて自分なりに想像したうえで、「どんな感情を抱いたのか?」「その後どんな行動をとったのか?」などの質問を相手に投げかけられる状態です。 相手は受け取った質問に対して、さらに深堀した内容を話してくれるので、比較的濃いコミュニケーションが取れるようになります。 レベル④:相手の感情を想像して、言語化してあげられる状態 共感力MAXの状態です。これができると、相手から絶大な信頼が寄せられます。相手が「どんな感情を抱いたのか?」「その後どんな行動をとったのか?」を想像したうえで、「もしかしたら〇〇だと考えたんじゃない?」と、言語化することができる。そしてその言語化した内容がドンピシャで相手が思っていたこととシン
日記という「感情のアルバム」をつけないわけにはいかない
今回は日記について話したいと思います。 みなさん日記って書いてますか? 僕は、今年の7月ごろから、ゆーてまだ5カ月ほどではあるんですが、日記を毎日書いています。 日記書くのって結構めんどくさいですよねー。故にめちゃくちゃ挫折しがちです。 この記事を見ている人にも、日記に挑戦したけど挫折した方はいるんじゃないかなーと思います。 現に僕も、過去10回ほど挫折してます。だいたい1週間くらいしか継続できなくて、自分の意志力の無さに打ちひしがれた経験がめちゃくちゃあります。 今は5カ月と、過去類をみないほど長く継続できています。たぶんこのままずっと習慣化できるんじゃないかなー。 んで、本題なんですが、単調直入に言います。 日記はマジで、テキトーでもいいんで書いた方がいいです 日記って、人生変えるんじゃないかレベルの習慣な気がします。 死ぬほど挫折してきた僕が、5カ月間継続してみて日記ってスゲーっ!と感じたので、おそらく間違いないです。 日記を書いた方がいい理由 なぜ僕がここまで日記を推すのか、それには2つの理由があります。 ①俯瞰で人生を見れること②アウトプットの習慣ができること この2つです。「たった2つだけ?」と思われるかもしれないですが、この2つがとてつもなくでかいです。 少し深堀して話します。 ①人生を俯瞰で見れる 毎日日記をつけることで、その日起こったことや思ったことを後から振り返ることができます。 そうすると、自分の成長や変化に気づくことができるんですね。 日記をつけておらず、常に今の自分のことしか知らない状態だと、なかなか自分の変化に気づくことって難しいです。 でも、日記をつければ過去を振り返ってみて、自分がどれほど成長したか、変化したかがわかるようになります。 シンプルにモチベーションめっちゃ上がるし楽しいんですよね。 僕自身、高校生の時に書いていた日記(1週間くらいで挫折してた時のやつ)を見返したんですが、「好きな人に振られてマジ辛すぎて死にたい」みたいなことが書いてあって、「ふんっ、若造が」と、過去の自分を嘲笑しました。 当時に比べると自分はめちゃくちゃ大人になりましたね。 といった感じに、自分の成長を感じられるしシンプルに面白いです(笑) また、日記として書くことによって、客観視点で自分の状況を確認できます。それによって結構メンタルの安定にも繋がったり
あなたは「努力したって報われない」のか?少し深堀して解説してみる
某有名女性アイドルグループのT橋みなみさんは、総選挙の時のスピーチでこのような名言を残していました。 「努力は必ず報われる」 素晴らしい言葉ですね。しかし、この発言には賛同する意見もありつつ、「努力なんてしてもほとんどの人が報われることなんてない」 といった否定的な意見も一部見られます。 確かに努力をしたことですべての人が成果を出しているならば、この世はもう少し成功者で溢れるようになる気がします。 「努力しても、成功できなかった」という風に考える方は一部いるのはうなずけます。 ただ、おそらくこの食い違いは「努力」「報われる」の個人間の定義の差によるものだとAkitoは考えてます。 「努力」「報われる」を主観的に捉えるとハードルはぐっと下がる 否定的な意見の人は、恐らく「報われる」を客観的に捉えすぎています。 具体で表すと 「報われる」=他社から見て、尊敬されるほど金銭的・社会的に成功を収める。といった感じです。 もっとわかりやすく言うと・めっちゃ稼いでる・メディアに出る有名人になる 的な感じですね。 この定義にすると、確かに報われない人がほとんどだと思います。 もっと主観的にとらえて「報われる」を考えてみましょう。 「自分が楽しいと思えるものを見つけて、それをより一層レベルを上げるために努力をする。その努力をする過程で、やりがいを見出し満足度の高い人生を送ることができている。」 ちょっと長くなりましたが、こんな感じです。めっちゃ報われている感じがしませんか? しかもこれは金・名誉などの他人の物差しで自分を測っていないので、考え方次第で、だれでも達成できると思われます。 楽しいと思うものを見つけて、さらにやりがいを見出せている状態になるプロセスは? 自分が楽しいと思えるものを見つける。こればかりは、すみません、ひたすらいろんなものに挑戦してください。 結構脳筋です。 近道とか裏技とかありません。 とにかくいっぱい行動して、たくさんのチャレンジをしてください。 ひとつテクニックを教えると、自分の感情を観察してみてください。新しいことにチャレンジしたときは、日記をつけてみるのもいいかもしれません。 「明日もやりたいと思った」とか「どうすればうまくなるか自然と考えちゃってた」とかポジティブな感情が生まれているものに注意深く着目してください。 そして、もし楽しいと思えるもの
細かいことを考えすぎると、何も前に進まないんやで。。。
こんばんは。ばんぶうです。 最近めっきり寒くなって、冬本番って感じになってきましたね。 さて、今回は考え方について少し話していこうかなと思います。 今回は考え方のコツは、”モジュール化”することがおススメという内容で書いていこうかなと思います。 モジュール化とは主にプログラミングとかで使われる言葉です。 単一の機能を持ったいくつかの要素ををまとめて、一つの機能をもつより大きな要素にすることです。 わかりやすくガンプラに例えると、 細かい1つ1つのパーツを組み合わせて、1つの機能を持つ腕を作ります。この場合腕が”モジュール化”されたものとなります。 具体的で細かい要素をまとめ上げ、より大きな1つの概念に抽象化することが”モジュール化”ということになります。 最近、半導体の仕組みを説明する動画をYouTubeで見たのですが、その時に”モジュール化”が頻出してました。 半導体が、今日、世の中のいろんな電子機器に活用されているのはモジュール化による恩恵だと、その動画で説明されていたのですが、 「”モジュール化”ってすげぇ!!!!」って心の底から感動しちゃったんですよね。 それと同時に、「”モジュール化”の考え方ができると、たぶんめちゃくちゃ仕事ができるようになるな」とも思いました。 というか恐らく世の中にいる、仕事ができていると評価されている人間ってぜっっったいに”モジュール化”の達人だと思うんですよね。 んでもって、仕事ができない人は逆に”モジュール化”ができない。 全ての事象を個別具体で考えてしまう⇩それによって仕事の進みが遅くなってしまう⇩時間が無くなり成果物の質が悪くなる みたいな感じでどんどん悪循環になってしまうんですね。 僕自身、もともと”モジュール化”の考え方はしてました。その最たる例は自らのマーケティング思考に表れている気がします。 マーケティングって突き詰めたら、①誰に②何を③どう伝えるかの3つしかないんですね。 もちろん細かく考えることもできるんですが極論この3つしかないです。3C分析とかSWOT分析とか、なんかいろいろフレームワークがありますが全て上の3つを決めるための材料にしかなりません。 ”モジュール化”は複雑な事象をシンプルにして、行動や決断を早めるためにも重要なんですよね。 今後、情報量は今以上のどんどん加速していくでしょうし、複雑な事象を複
インプットで満足してしまう現代人
こんにちは。ばんぶうです。 インプットってね、麻薬ですよね。 学生時代は、勉強することがもてはやされていましたし、社会人になってからも自分の成長のため、学習やリスキリングを行う人も結構増えている印象です。 しかし!インプットなんてたとえ10000時間やったとて、何も生み出さないんですよね、これが。 それなのに最近はインプットすることに満足してしまう人が多いこと多いこと。 あなたは、インプットしてますか?それとも”アウトプット”もしっかりしていますか? 今回はインプットのことについてお話ししようと思います。 現代人はインプット病?インプットばかりしてしまう理由とは 結論これは、”インプットはめちゃくちゃ楽”だからに尽きると思います。 インプットって基本的に受け身の形になります。YouTubeで動画見るしろ、ビジネス書を読んで知識を取り入れるにしろ、自分なりに考えたりせず、「へー、そうなんだ!」と鵜呑みにするだけで、インプットとしては成立しちゃいます。 また、現代は情報過多の時代になってます。なーんにも考えずに、毎日ぼーっとしているだけでも、スマホを開けば何かしらの情報が脳みそに入ってきてしまうのです。 自ら「インプットしよう!」と思い立たなくても、勝手にインプットが”されてしまっている”状態になるので、インプットばかりになってしまうんですね。 何も生み出さいインプットの化け物 先ほどもお伝えした通り、インプットというのは基本受け身です。誰かが発信した情報を受け取る側になります。 基本的に社会は情報を発信している側がお金を儲けられる仕組みです。あなたが毎日見ているユーチューバーも、読んでいる本も、学んでいる教材も、必ず誰かが情報を発信しています。 そして、情報を発信している人はその対価としてお金をもらっています。 ここで、勘のいい人は気づくと思いますが、この社会はアウトプットして初めて価値が生まれます。 アウトプットに値段がつけられる仕組みになってます。 「俺、めっちゃ情報をインプットしたから、その報酬でお金くれよ!」はまかり通りません。 あくまでインプットというのは、情報を取り入れて知恵にすることでインプットを強化する立ち位置という意識でいた方が良いと思います。 アウトプット習慣を始めてみよう とはいえ、アウトプットするのって難しいですよね?インプットするより、数倍
憧れの人がいることは必ずしも正義ではない
よく巷ではこんな言葉が言われています。 「人生を変えるなら目標とする人を作ったほうがいい」「憧れている人をコピーすれば成長する」 あなたも一度は見たことがあるフレーズだと思います。 でもこれ、僕は妄信してはいけない言葉だなと思います。憧れの人がいることが”良いこと”というのは半分正解、半分不正解なんです。 この理由はほんとに単純で、①憧れてしまった以上、その人を超えることができない②真似するだけでは単なる劣化版コピーになってしまう の2つに集約されます。 これは僕自身の実体験です。僕は以前は憧れの人を作って、その人を真似することが自分のスキルアップに一番の近道と考えていました。この憧れの人にあたるのは僕の上司になります。 ひたすら憧れている人の真似をすることは、最初の成長のスピード感は確かにあるかもしれません。 でもある程度、自分に力が付いた時にふと思うんです。「なんだか、憧れの人に近づいている感じがしなくないか、、?」僕自身この違和感にずっと悩まされてました。 ただこれってすごく単純なことで、要は ”憧れの人と自分とでは、それまで培ってきた経験も知見も人間性も違うから、目に見える表面上の部分を真似したとしても、その人になることはできない”からです。 そしてもう一つの理由は、憧れが成長の限界点になるからです。 これって割と気を使いがちな人にあるあるなんですが、当初、憧れていた人にスキルやポジションが近づき、抜いてしまうような感覚を覚えたら、わざと手を抜いたり、できないふりをして、その人を抜かないように意識や行動を調節をしてしまったりしませんか? これは意識してやっていなくても、無意識で上記のようになってしまうんです。 仮説ですが、・憧れの人を超えてしまう忍びなさ・超えた後の目指す先がなくなるのが不安という2つの要素が自らをそういう動きにさせてしまうんだと思います。 「今憧れている人がいるんだけど、どうすればいい?」そんな方は、考え方を変えればいいです。 憧れの人は真似をしようとしてはダメです。優れていると思うことを盗む意識でいてください。 優れている部分をエッセンスとして自分の中に取り込むとどんな風に成長できそうか。それだけを考えていればいいです。 あくまで、目標・憧れとする人物像は”憧れのあの人”ではなく、”理想を叶えた自分”でいてください